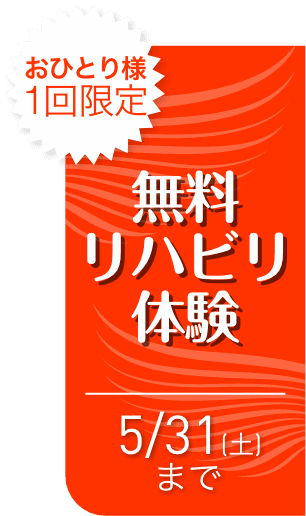こんにちは!京都にある自費リハビリセンターを運営しています。
センター長の米田です。
今日は心臓の前負荷と後負荷についてです。
前負荷とは
前負荷は、心室が収縮する前に心室にかかる負担を指します。具体的には、心室が拡張しているときに流入する血液の量、すなわち拡張期末期の心室容積(ventricular end diastolic volume)によって決まります。前負荷が大きいほど、心筋はより強く収縮し、より多くの血液を動脈に送り出すことができます。このため、前負荷は「容量負荷」とも呼ばれます。
前負荷を決定する要因には、静脈から心臓に戻る血液の量(静脈還流量)や心房の収縮力が含まれます。例えば、脱水や出血によって循環血液量が減少すると、前負荷も減少します。
後負荷とは
後負荷は、心室が収縮を開始した後に心室にかかる負担を指します。これは、心室が血液を動脈に送り出す際に直面する抵抗、特に大動脈圧や肺動脈圧によって決まります。後負荷は「圧負荷」とも呼ばれ、心室が血液を押し出すために克服しなければならない圧力を反映します。
後負荷が増加すると、心筋はより強く収縮しようとしますが、これが心拍出量の減少を引き起こすことがあります。高血圧や動脈硬化などが後負荷を増加させる要因となります。
前負荷と後負荷の関係
前負荷と後負荷は、心臓の拍出量に対して相互に影響を及ぼします。前負荷が増加すると心拍出量が増加する一方で、後負荷が増加すると心拍出量は減少する傾向があります。このため、心不全などの病態では、これらの負荷を適切に管理することが重要です。
心不全の治療では、前負荷を軽減するために利尿薬が使用されることが多く、後負荷を軽減するためには血管拡張薬が用いられます。これにより、心臓の負担を減らし、機能を改善することが目指されます。
リハビリテーションの効果
1. 心機能の改善
リハビリテーションは、心臓の機能を改善するための運動療法を含みます。運動は心筋を強化し、心臓のポンプ機能を向上させることが知られています。特に、心不全患者においては、運動が心臓の後負荷を軽減し、末梢の血液灌流を増加させることが示されています。
2. 生活の質の向上
心臓リハビリテーションを受けることで、患者の生活の質が向上することが多いです。運動により体力が向上し、日常生活での活動が楽になるため、患者はより自立した生活を送ることが可能になります。
3. 再入院率の低下
リハビリテーションを受けた心不全患者は、再入院率が低下する傾向があります。定期的な運動と医療者の監視のもとでのリハビリは、心不全の悪化を防ぐ効果があります。
4. 心理的な効果
運動は身体的な健康だけでなく、精神的な健康にも良い影響を与えます。リハビリテーションを通じて、患者はストレスを軽減し、うつ症状の改善が期待できます。
リハビリテーションの実施方法
リハビリテーションは、医療専門家の指導のもとで行われることが重要です。以下のような方法が一般的です:
- 運動療法: 有酸素運動や筋力トレーニングを組み合わせたプログラムが推奨されます。
- 栄養指導: 健康的な食生活を促進し、心臓に優しい食事を提案します。
- 教育: 心不全や心臓病についての理解を深め、自己管理能力を高めるための教育が行われます。
リハビリテーションは、心不全や心臓病の患者にとって、心機能の改善や生活の質の向上に寄与する重要な治療法です。定期的な運動と医療者のサポートを受けることで、患者はより良い生活を送ることができるでしょう。
京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!
ご利用者様の身体状況に合わせてリハビリを進めていきます。
エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓
経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。
また、脳卒中後遺症による麻痺だけではなく、パーキンソン病などの神経性障害や、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの運動器疾患、慢性疼痛など様々なお身体の悩みに対しても対応させて頂いております。
現在、エール神経リハビリセンター伏見ではリハビリ体験を実施しております。
リハビリ体験はこちら↓
特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)
LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓

https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true
お電話でのお問い合わせも対応しております。
お気軽にお問い合わせください。