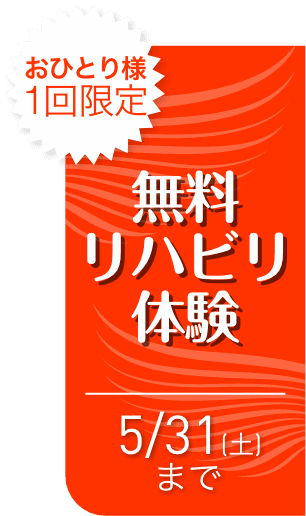1. はじめに:パーキンソン病のリハビリに悩むあなたへ
「手が震える」「歩きにくい」「声が小さくなった」──これらは、パーキンソン病の方が日常でよく感じる症状です。進行性の病気であることから、「もう良くならないのでは」と不安を抱えておられる方も少なくありません。
しかし、希望はあります。リハビリテーションによる継続的な身体機能の刺激は、症状の進行を遅らせたり、生活の質を保つうえで非常に重要です。特に京都では、地域医療と連携した保険診療によるリハビリだけでなく、より個別性・専門性の高い自費リハビリを選択される方も増えています。
私は京都市で自費リハビリのセンター長を務める理学療法士として、パーキンソン病の方と日々向き合い、身体だけでなく「こころ」にも寄り添うサポートを行っています。これまで多くの方のリハビリを支援してきた中で、運動療法だけでなく、栄養や神経伝達物質に関する知識も重要であることを強く感じています。
そこで本記事では、**パーキンソン病と関わりの深い「ドーパミン」とその材料となる「チロシン」**というアミノ酸に着目し、リハビリの新たな視点をお伝えします。
京都でリハビリに励む方、あるいはご家族の方にとって、本記事が希望と実践的なヒントになることを願っています。
2. 現状:京都のリハビリ業界とパーキンソン病への取り組み
2-1. パーキンソン病のリハビリ、現状と課題
京都市内には多くの医療機関や通所施設があり、パーキンソン病に対する理学療法や作業療法が提供されています。これらは主に保険診療による標準的な運動療法で、歩行訓練やバランス練習、筋力トレーニングなどが中心です。
しかし、保険制度上の制約(週に数回、1回20分程度の短時間)により、「もう少し丁寧に診てほしい」「身体だけでなく心や生活にも踏み込んだサポートが欲しい」と感じる方も多くいらっしゃいます。また、進行性疾患であるがゆえに「少し良くなっても、すぐに戻ってしまう」との不安や、効果が感じにくいという声も少なくありません。
そうしたなかで注目されているのが、自費リハビリという選択肢です。保険の制限を受けず、より時間をかけた個別対応が可能であるため、利用者のライフスタイルに合わせた柔軟なプランや、食事・運動・心理面を含めた総合的なアプローチが実現できます。
京都においても、こうしたパーソナライズされた自費リハビリを求める動きは着実に広がっており、当施設にも市内外から多くのパーキンソン病の方がご相談にいらっしゃいます。
2-2. なぜ「チロシン」に注目するのか?
パーキンソン病は、脳内の「黒質」という部位の神経細胞が減少し、「ドーパミン」という神経伝達物質が不足することで運動機能に影響を及ぼす病気です。ドーパミンが足りなくなると、手足のふるえ(振戦)や筋肉のこわばり(固縮)、動作の遅れ(無動)などが現れます。
この「ドーパミン」は、実はある栄養素から作られています。その材料となるのが、「チロシン(tyrosine)」というアミノ酸です。チロシンは体内で生成される「非必須アミノ酸」でありながら、神経伝達物質の生成において重要な役割を担っています。
ドーパミン補充薬(L-ドーパ)を用いた薬物療法は一般的ですが、体内のドーパミン合成の“土台”であるチロシンの存在に目を向けることは、より自然なかたちで症状を緩和し、日常生活の質を高めるためのヒントになるかもしれません。
当施設では、運動リハビリだけでなく、チロシンを含む栄養学的アプローチも踏まえ、より多面的にパーキンソン病の方の生活をサポートする取り組みを進めています。
3. 深掘り:パーキンソン病に効くと言われる「チロシン」のメカニズム
3-1. チロシンとは?心と身体に与える良い影響
チロシン(tyrosine)は、体内でフェニルアラニンから合成される非必須アミノ酸の一つです。タンパク質を構成する成分としてだけでなく、さまざまな神経伝達物質の「原料」となる働きを持ち、特に脳の機能とストレスへの耐性に深く関わっています。
近年では、以下のような効果が報告されています:
集中力の向上
ストレス耐性の強化
注意散漫の防止
気分の安定化
これらは、特にパーキンソン病の方にとって重要な要素です。なぜなら、運動機能だけでなく精神面の低下(うつ傾向や無気力)も病状の一部であるからです。
また、チロシンは発育期の子どもにも不可欠な成分です。先天的にチロシンが生成できない「フェニルケトン尿症」という病気では、重度の知的障害を引き起こす可能性があることからも、その重要性がうかがえます。
3-2. 幸せホルモン「ドーパミン」とチロシンの関係
ドーパミンは「やる気」や「達成感」「快感」に関係する神経伝達物質であり、いわゆる“幸せホルモン”の一種です。私たちが何かに挑戦しようとする意欲や、楽しさを感じる瞬間にこのドーパミンが働いています。
パーキンソン病では、このドーパミンが著しく減少するため、
「やる気が出ない」
「笑顔が減った」
「何をしても楽しく感じない」
といった精神的な症状も現れやすくなります。
そして、そのドーパミンを体内で合成する際に欠かせない材料が、チロシンです。チロシンが不足していれば、当然ドーパミンも作られにくくなり、症状の悪化を招く可能性があります。
また、近年ではチロシンの抗うつ作用も注目されており、精神的な安定を支える栄養素としても非常に有用です。
3-3. やる気を出す「アドレナリン」の材料にもなるチロシン
チロシンは、ドーパミンだけでなくアドレナリンやノルアドレナリンといった神経伝達物質の前駆体でもあります。
アドレナリン:瞬発力、危機対応、やる気スイッチ
ノルアドレナリン:集中力、思考のクリアさ、緊張感のコントロール
これらが不足すると、次のような症状が現れやすくなります。
無気力感
慢性的な疲労感
集中力の低下
抑うつ的な気分
つまり、チロシンは**「心のアクセル」とも言えるホルモンたちの材料**となる栄養素であり、パーキンソン病の方に多く見られる精神的な低下へのアプローチとして非常に注目されています。
3-4. 体の調子を整える「甲状腺ホルモン」とチロシン
あまり知られていませんが、チロシンは甲状腺ホルモン(T3、T4)の材料でもあります。
甲状腺ホルモンは、
新陳代謝の調整
エネルギーの消費促進
体温調節や心拍数の維持
など、全身の活力に関わる非常に大切なホルモンです。チロシンが不足すると、甲状腺ホルモンの合成にも支障が出る可能性があり、疲れやすさ、冷え、やる気の低下など、パーキンソン病の症状に似た状態を助長することがあります。
このように、チロシンは「脳・心・身体」すべてに関わるアミノ酸と言っても過言ではありません。
4. 実践:京都でチロシンを活かしたリハビリを目指すために
4-1. 効果的なチロシンの摂取方法
チロシンはサプリメントでも摂取可能ですが、基本的には日常の食事から自然に摂るのが理想的です。特に以下のような食品に多く含まれています。
チロシンが豊富な食品例:
タケノコ(白い粉状の結晶はチロシンそのもの)
かつお節
納豆
アーモンド・ピーナッツ
牛乳・ヨーグルト・チーズ
卵
鶏肉・豚肉・牛肉
タケノコを茹でたときに出てくる白い粉は、実はチロシンの結晶です。古くから日本の食文化に取り入れられてきた食材の中に、自然と脳機能をサポートする栄養が含まれていたのです。
また、トリプトファン(セロトニンの材料)との同時摂取もおすすめです。たとえば、納豆ごはんやチーズ入りオムレツなど、和洋問わず組み合わせの工夫で相乗効果が期待できます。
注意点:
チロシン+炭水化物の大量摂取は、吸収を妨げる可能性があるため注意が必要です。
タンパク質中心の食事を意識しながら、栄養バランスを整えることが鍵です。
4-2. チロシン摂取における注意点と副作用
通常の食事から摂るチロシン量で副作用が起こることはほとんどありませんが、サプリメントによる過剰摂取には注意が必要です。
過剰摂取によるリスク:
1日1,000mg以上の摂取で、まれにシミや色素沈着が起こるという報告あり(ビタミンC不足との関連が指摘されています)
チロシンを摂取する際には、ビタミンCやミネラルとの併用が望ましいとされています
さらに、ごく稀な例として「高チロシン血症」という遺伝性代謝異常があります。これは、体内でチロシンが正常に分解されず蓄積してしまう疾患で、下記のような症状が現れることがあります。
発達の遅れ
肝機能障害
皮膚の異常
この疾患が疑われる場合は、必ず専門医の診断を受け、医師の指導のもとで食事療法を行うことが必要です。
4-3. 京都の自費リハビリ施設でできること
当施設では、パーキンソン病の方に対し、運動療法と栄養指導を組み合わせたリハビリを行っています。具体的には、以下のような取り組みをしています。
▷ 提供しているサービス内容:
姿勢改善や歩行の安定化を目的としたマンツーマンの理学療法
日常生活の中でのストレスコントロール方法の指導
ご家族へのサポート提案やセルフケア指導
パーキンソン病は、単に「運動がうまくできなくなる病気」ではありません。意欲の低下や自律神経の不調、栄養バランスの崩れなど、心身にまたがる課題を抱えることが少なくありません。
だからこそ、私たちのリハビリは**単なる運動指導ではなく、栄養・心・生活習慣を含めた「包括的な支援」**を目指しています。
患者様一人ひとりの状態や生活スタイルを丁寧に伺いながら、チロシンを含めた神経伝達物質の働きに着目したリハビリ提案を行い、前向きな変化を支援しています。
5. まとめ:京都でパーキンソン病と向き合い、希望ある未来へ
パーキンソン病は、進行性でありながらも、正しいリハビリと生活習慣の見直しで“生活の質”を維持・向上できる病気です。本記事では、そのリハビリに新たな視点を加えるべく、「チロシン」というアミノ酸に注目しました。
チロシンは、ドーパミンやアドレナリンなどの神経伝達物質の原料となり、運動機能だけでなく、「やる気」「幸福感」「集中力」など、心の健康にも大きな影響を与えます。さらには、甲状腺ホルモンの材料となることで代謝を支えるという多面的な効果があるのです。
京都でパーキンソン病に悩む方々にとって、リハビリはただの訓練ではなく、**身体と心を整えるための“再出発のきっかけ”**であるべきだと、私たちは考えています。
当施設では、単に運動だけを行うのではなく、チロシンをはじめとする栄養への配慮、生活スタイルの見直し、心へのケアを一体として取り組み、利用者様とそのご家族が「前向きに、生き生きと暮らせる未来」を目指しています。
📌 京都でパーキンソン病のリハビリに悩んでいるあなたへ
「最近、動きがぎこちなくなった気がする」
「気持ちが沈みがちで、何もやる気が起きない」
「病院のリハビリだけでは物足りない」
そんなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ一度、専門家に相談してみてください。私たちは、あなたの生活の中にある「小さな変化」に寄り添いながら、できる限りのサポートをいたします。
京都のエール神経リハビリセンターでは、病気によって今後の生活が不安なあなたに寄り添います。オーダーメイドで適格な運動プランの提案や訓練を提供!
京都での自費リハビリが、あなたの未来の一歩になります。
エール神経リハビリセンターの動画はこちら↓↓↓
経験豊富な理学療法士・作業療法士がチームを組みご利用者様の思いを実現できるよう最善を尽くします。ご興味があれば体験に来ていただけると嬉しいです。
【Q&Aコーナー】
Q1. 気温変化で体調が悪くなった場合、リハビリは休んだ方が良いですか?
A1. 無理をしてリハビリを行うとかえって体調を崩す原因にもなりかねません。体調が優れないと感じたら、まずは担当の理学療法士にご相談ください。状態に合わせて、内容を調整したり、休息を勧めたりします。
Q2. 自宅でできるストレッチは、毎日どのくらい行えば良いですか?
A2. 毎日継続することが大切です。無理のない範囲で、各ストレッチを10~20秒程度、2~3セットを目安に行ってみましょう。朝起きてすぐや、お風呂上がりなど、身体が温まっている時間帯が効果的です。
関連キーワード
- 脳卒中リハビリ 京都
- パーキンソン病 ストレッチ 京都
- 京都 リハビリテーション
- 自費リハビリ 京都
- 麻痺 リハビリ 京都
- 痙縮 ストレッチ
お問い合わせ・ご予約
現在、エール神経リハビリセンター伏見ではリハビリ体験を実施しております。
リハビリ体験はこちら↓
特別リハビリ体験のご案内 | エール神経リハビリセンター 伏見 (aile-reha.com)
LINEでもお気軽にお問合せ下さい↓

https://page.line.me/993lksul?openQrModal=true